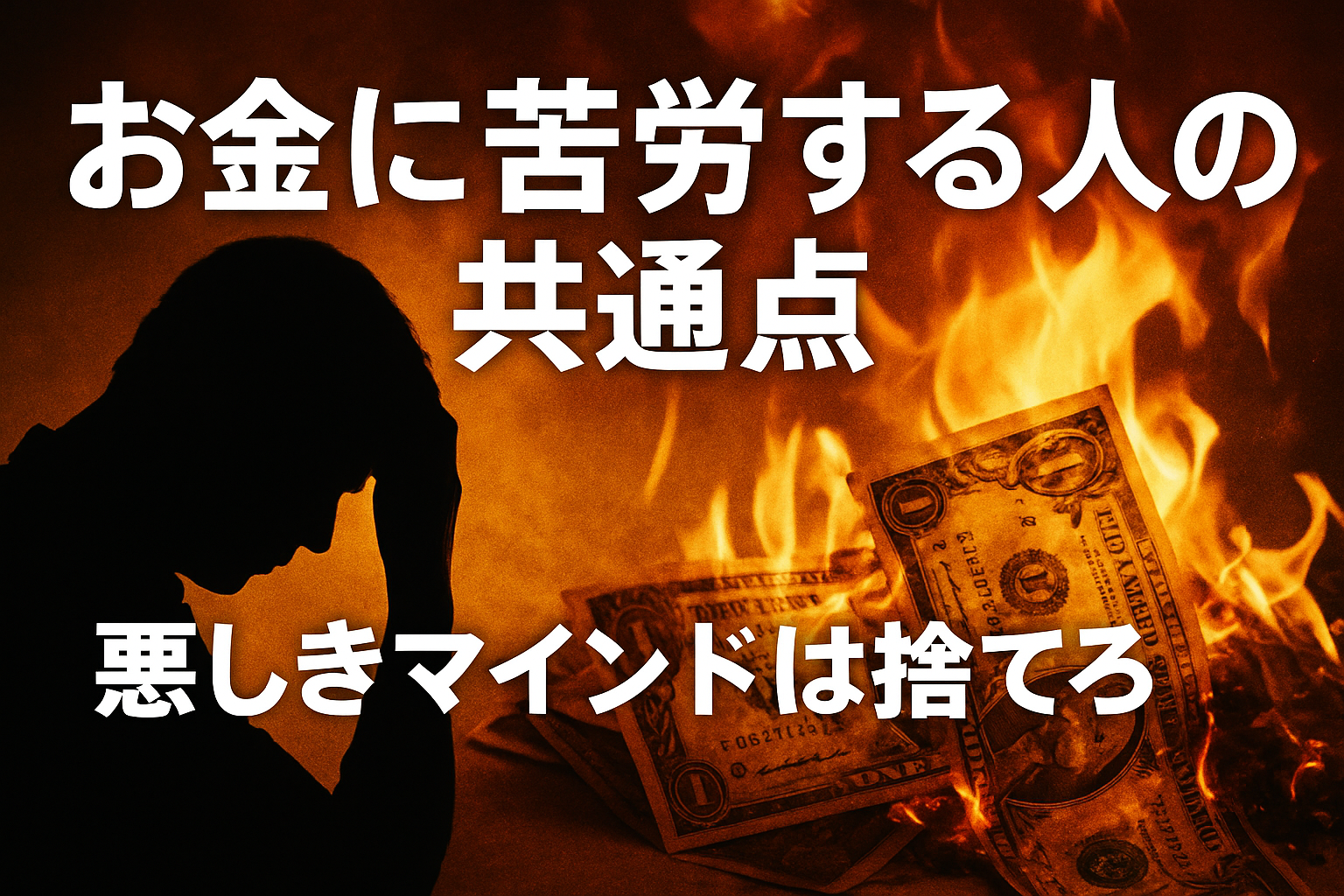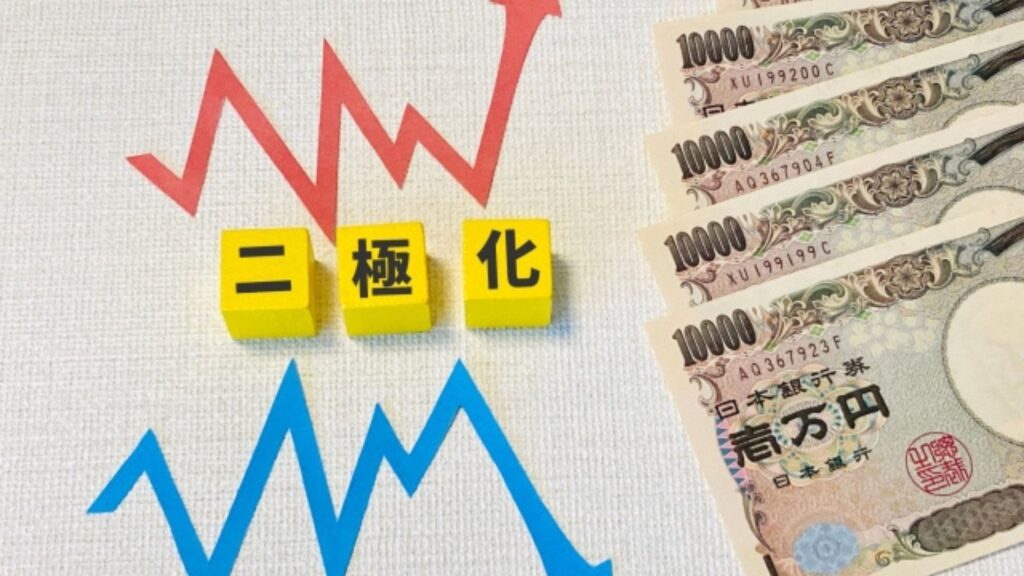
節約しているはずなのに、なぜかお金が貯まらない。
ボーナスが出ても、いつの間にか消えてしまう──。
このように「頑張っているのに報われない」と感じる人も多いのではないでしょうか。
実は、お金に苦労する人には共通する5つの習慣があります。
これは能力や収入の差ではなく、考え方と行動のクセに原因があるのです。
この記事では、今日から直せる「お金に愛される思考と習慣」を紹介します。
ぜひ最後まで読んでいただけると嬉しいです。
お金が残らないのは、収入のせいじゃない
「収入が少ないから貯まらない」
──確かに、それも一理あるでしょう。
しかし、年収が上がっても貯金が増えない人はたくさんいます。
逆に、平均的な収入でもしっかり資産を築いている人もいます。
その違いは「収入」ではなく、お金に対する習慣と考え方にあります。
では、実際に収入と貯金の間にはどんな関係があるのでしょうか?
収入と貯金の関係
金融広報中央委員会という謎の組織が公表している「令和5年の家計の金融行動に関する世論調査」によると、収入と貯蓄率が確認できるデータがあります。
二人以上世帯の金融資産保有額(令和5年)
年収300万円~500万円未満・・・貯蓄率20%以上の世帯が15,5%
年収1,000~1,200万円未満・・・貯蓄率0%の世帯が18.8%
二人以上世帯の年収300万円~500万円の世帯で、貯蓄率20%以上の世帯が15,5%いるのに対して、年収1,000~1,200万円未満の世帯で貯蓄率0%の世帯が18.8%もいます。
ちなみに、集計最上位の1,200万円以上の世帯の19.5%は貯蓄率0%という結果でした。
つまり、収入が高くても、お金が残らない人は少なくないのです。
人は収入が増えると、
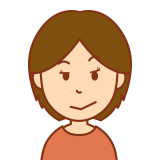
今より少し良い暮らしをしたい
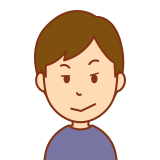
稼いでいるから、これくらい使ってもいい
という欲求が自然に強まります。
──この考えが貯蓄を遠ざける最大の罠です。
収入が増えても貯金が増えない理由
これは「パーキンソンの法則」と呼ばれ、収入が上がるほど支出も増えてしまう人間の傾向を示しています。
具体的なケースで説明します。
年収が400万円から500万円にアップしたとします。
すると、理論上は100万円を貯金に回せるはずです。
収入として毎月約8万円増える計算ですが、収入が増えたことでお金と心に余裕ができます。
たとえば、こんな経験はありませんか?
最初は「ご褒美」のつもりでも、気づけばそれが“当たり前の生活”になるのです。
この結果、収入と支出が比例して増えていくため、貯金が増えない。
「収入を増やす」よりも「支出をコントロールする」方がはるかに難しいのです。
生活レベルを上げるより、余白を作る
収入が上がったときこそ、生活水準を上げる前に「余白」を意識しましょう。
収入が5万円増えたなら、
このように“使う割合を決める習慣”が、将来の安心を生み出すでしょう。
豊かさとは「多くを持つこと」ではなく、「使わずに済む余裕」を持つことです。
お金が残る人が実践している“仕組み”
お金が貯まる人は、意志ではなく「仕組み」で動かしています。
たとえば
- 給与日に自動で貯蓄用口座に振替設定
- 固定費(保険・通信・サブスク)を定期的に見直す
- 余剰分は即座に投資や積立へ回す
これらは一見地味ですが、“考えなくても貯まる”流れを作る行動です。
お金の管理を感覚ではなくルール化すれば、意志の強さに頼らず貯蓄が続きます。
金を貯める人は「節約している人」ではなく「仕組みを作った人」なのです。
お金に苦労する人の共通習慣5選
お金に苦労する人の特徴は、収入の多さよりも「習慣」にあります。
お金を使うときの心理、周りとの付き合い方、情報への向き合い方、すべてが“お金の流れ”に影響しています。
ここでは、お金が逃げていく5つの習慣を紹介します。
どれか一つでも当てはまるなら、今日から意識を変えるチャンスです。
その1 自己肯定感をお金で満たそうとする
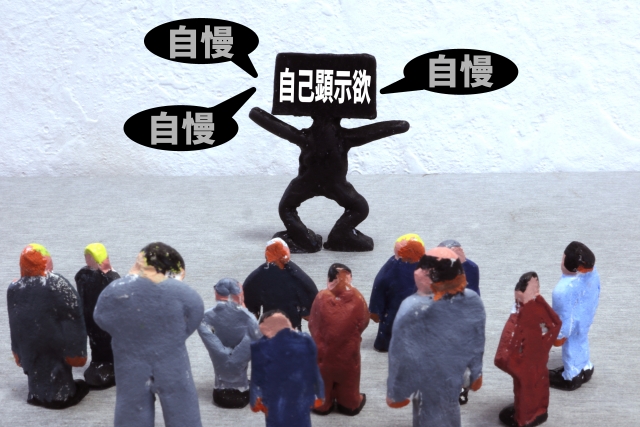
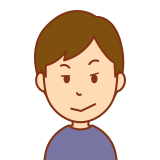
頑張った自分を認めてほしい
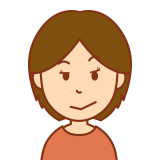
綺麗、可愛いと言われていたい
この感情は誰にでもあります。
しかし、お金に苦労する人ほど、“お金を使うことで自己肯定感を満たそうとする”傾向があるでしょう。
たとえば
これらは一見、前向きな消費に見えても、実際には「他人からの評価」に依存しています。
その結果、お金を使っても満たされず、さらに浪費が増えるループに陥ります。
真の自己肯定は「お金を使うこと」ではなく「お金を守れる自分」になることです。
その2 飲酒や付き合いにお金を使いすぎる
「断れない」「ストレス解消したい」
そんな気持ちから飲み会や交際費にお金を使いすぎてしまう人は多いでしょう。
一度きりの出費なら問題ありませんが、これが「習慣」になると、家計にも時間にも大きな影響を及ぼします。
金銭的コストと時間的コストの両方が積み重なる
たとえば、
飲み会の回数や付き合いは、「出費」よりも「連鎖的影響」が大きいのです。
トラブルや健康への影響も考える
お酒の席では、気が緩みやすく、判断も鈍ります。
その結果
短期的には“楽しい時間”に見えても、中長期的には「お金」「信頼」「健康」という3つの資産を失うリスクがあります。
賢いお金の使い方とは「今の快楽」ではなく「未来の自分」へ投資することです。
“控える選択”が“失わない選択”につながるのです。
その3 脳を支配する悪習慣に時間とお金を奪われる
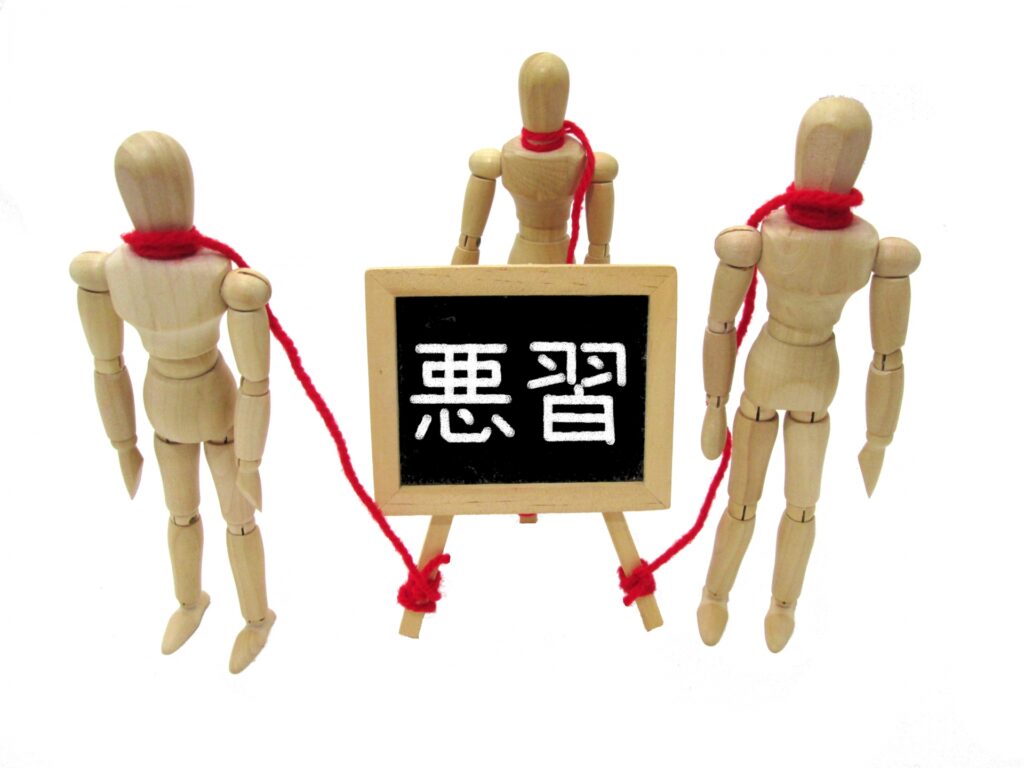
「少しだけ」「今日くらいはいいか」
そうしてつい手を出してしまう“習慣的な快楽”は、気づかぬうちに脳・時間・お金を同時に蝕んでいくでしょう。
具体的には次のようなことです。
- SNSでいいねをもらうための行動
- タバコ
- ギャンブル
- 夜のお店
どれも最初は「リフレッシュ」や「ストレス発散」のつもりでも、それが“脳”を刺激し続け、依存のスパイラルを生むのです。
脳が“報酬”を求め続ける仕組み
SNSの「いいね」通知、ギャンブルの一瞬の興奮、お酒や夜のお店での非日常の時間。
これらはすべて脳の「ドーパミン」を刺激します。
すると脳は「もっと刺激を」と要求し、同じ満足を得るためにより多くのお金・時間を使うようになるでしょう。
つまり、“浪費”ではなく“報酬依存”が止まらなくなるのです。

どれも共通しているのは、「一瞬の満足」と引き換えに「長期の損失」を積み重ねているという点です。
つまり、“浪費”だけではなく“報酬依存”が止まらなくなる危険な習慣なのです。
依存から抜け出す3つのステップ
習慣を変えるには、意志よりも環境を変える方が確実でしょう。
1️⃣ 使用時間・支出を「見える化」する
まず、どの習慣にどれだけの時間とお金を使っているかを把握。
2️⃣ “置き換え習慣”をつくる
スマホの代わりに本を読む、ギャンブルの代わりにウォーキングをするなど、
“快楽の種類”を健康的な方向に変える。
3️⃣ 人と環境を変える
依存を強める仲間や環境は、意識的に距離をとる。
環境を変えれば、習慣も自然に変わるでしょう。
悪習慣をやめて、本当に大切なこと(健康・家族・自由)を取り戻しましょう。
その4 人間関係の選び方を間違える

お金に苦労する人ほど、関わる人を選べない傾向があるでしょう。
「断れない」「悪く思われたくない」といった心理から、自分にとってマイナスな人間関係を続けてしまうのです。
このように、自分の時間とお金を“他人の都合”で消耗している状態では、どれだけ収入が増えても、お金は貯まりません。
自分の人生は、付き合う人の“平均値”になるのです。
テイカー気質の人とは距離を置く
人間関係で最も注意すべきは「テイカー(Taker)」と呼ばれるタイプの人です。
テイカーとは
彼らは、最初は親しげに近づいてきます。
しかし次第に、

悪いけど、仕事手伝って
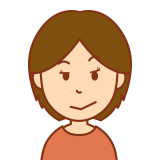
日程や場所、行程が決まったら教えて
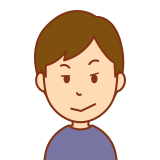
おごってよ
といった“依存的な関係”を築いてきます。
そして、こちらが与え続けるほど、彼らは感謝するどころか“要求をエスカレート”させていくのです。
テイカーとの関係は、自分の大切な「時間」「お金」「自信」が奪われるだけなのです。
私は
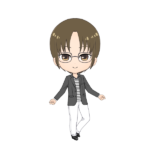
ただただお金と時間の無駄な関係だったな
としみじみ思っています。
良い人を近づけ、悪しき人を遠ざける勇気を持ちましょう。
距離を置くための3つのサイン
テイカーとの関係を切るのは勇気がいりますが、それは“損切り”ではなく“自分の人生を守る投資”です。
このようなサインが出たらその人と距離を置きましょう。
1️⃣ 頼みごとが多いのに、見返りがない
あなたが助けても、相手は当然のように受け取るだけ。
2️⃣ 感謝ではなく、愚痴や要求が増える
「ありがとう」より「もっとこうして」が口癖。
3️⃣ 一緒にいてエネルギーを消耗する
会った後に疲労感や違和感が残る人は、要注意。
逆に自分の時間やお金を「応援してくれる人」に使えば、それが自分に大きな力となって返ってくるでしょう。
“人間関係の棚卸し”が重要です。
その5 情報を受け身でしか得ようとしない
「誰かが教えてくれる」「ネットに書いてあったから安心」
そんな“受け身の姿勢”が、お金の失敗を生む最大の原因です。
世の中には無数の情報があふれていますが、受け身で得た知識ほど、理解が浅く、行動につながらないものです。
SNSや動画は便利ですが、発信者の意図や目的を理解せずに信じてしまうと「投資で損した」「怪しい情報に騙された」という結果を招きやすいでしょう。
金融・投資・節約などの情報は、質も方向性もピンキリです。
“受け身の学び”はリスクに直結します。
自分は賢いと勘違いしている
お金に苦労する人ほど、「自分は分かっている」と思い込みがちです。
ネットで見た情報や動画の知識を“理解したつもり”になり、実際の数字や制度を自分で確認しようとしないでしょう。
その結果、不要な支出を「お得な買い物」と勘違いする“痛い賢者”になってしまうのです。
「知っている」つもりが、「騙されやすい」状態を作っているのです。
- スマホを三大キャリアのまま契約し続けている
- 不要な保険に加入している(医療・終身・学資など)
- 賃貸退去時に高額な費用を請求されても「仕方ない」と諦める
- 証券会社の窓口で“おすすめ”と紹介された投資信託を購入している
どれも共通しているのは、「自分は賢く選んでいる」と思いながら、実際は情報に流されているという点です。
情報や知識が不足していると
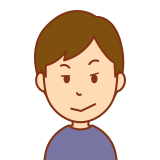
良い保険を安く契約できた自分は賢い
と錯覚してしまっています。
本当に賢い人は、広告や営業の言葉をうのみにせず、自分で調べ、比較し、理解した上で行動します。
「賢さ」とは、知識の多さではなく、確認する手間を惜しまない姿勢でしょう。
大事なことは行動すること
どれだけ知識を集めても、行動しなければ現実は1ミリも変わりません。
お金に苦労する人の多くは、情報を集めて満足してしまいます。
本を読み、動画を見て、「明日から頑張ろう」と思う。
実際に手を動かす人はごくわずかです。
知識が資産になるのは、「実行に移したとき」だけです。
学んだことを現実に落とし込むには、小さな行動から始めるのが一番です。
たとえば
たったこれだけで、「行動する力」が育ち始めるでしょう。
人は“行動できた成功体験”によって、次のステップに進めるからです。
頭で分かっていても動けない人と、よく分からなくてもまず動く人。
資産を築くのは、いつも後者です。
行動とは、情報の“最終確認作業”でもあります。
やってみることで、何が合っていて、何が違っていたのかが初めて分かる。
逆に言えば、行動しない人は一生「正しい答え」を見つけられないのです。
まとめ
お金に苦労する人の習慣・行動について解説しましたが、参考になれば嬉しいです。
お金に苦労する人と、着実にお金を増やしていく人の差は、収入の多さでも、運の良さでもありません。
その違いは、毎日の小さな「意識」と「行動の積み重ね」にあります。
お金に苦労する人は、
- 感情でお金を使い
- 他人の目を気にして支出を増やし
- 情報を鵜呑みにして行動を止める
一方で、お金を増やしていく人は、
- 自分の軸で判断し
- 習慣と仕組みで支出を管理し
- 不完全でも行動して学ぶ
お金を守る力とは、「選ばない勇気」と「動く覚悟」。
本当に人生を変えるのは、“使い方”と“動き方”です。
スマホ1つの契約を見直す、1つの支出をやめてみる──その一歩こそが、未来の大きな自由をつくるでしょう。
- お金に支配される人は「言い訳」を探す
- お金を自由にする人は「方法」を探す
今日から取る小さな行動が、未来の自分を豊かにする“最高の投資”になるでしょう。
お金に苦労しない自由な生活を送れるように一緒に頑張っていきましょう。